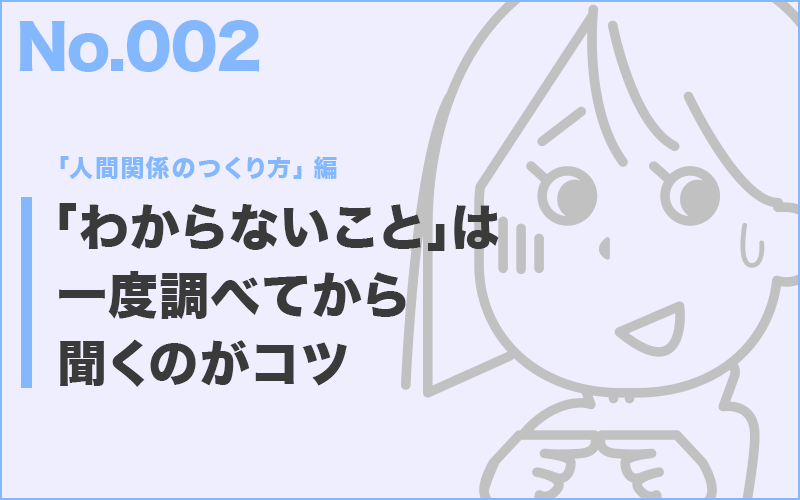今日もネットカフェからこんにちは。
コミュ力ゼロ美です。
皆さんは職場などで「わからないこと」があった時どうしますか?
知っている人に聞くのが一番はやいですよね。
でも質問によっては「こんな些細なこと聞いてもいいのか?」「流石に人に甘えすぎかな・・・。」
こんな風に迷うことあると思います。
実際に聞きすぎて「それは調べると出てくるよ」とやんわり注意されたり…なんて経験をされた人もいるのではないでしょうか。
今回は「わからないこと」についての立ち回りを学んでいきたいと思います。
もしよかったら参考にしてくださいね。
「わからないこと」は一度調べてから聞くのがコツ
渡瀬 謙著 「コミュ力ゼロからの「新社会人」入門」より
質問される側の心理を知っていこう
「わからないことがあったら何でも聞いてね」
やさしい先輩にそう言われたら安心しますよね。なんせ入社したばかりの頃は、わかっていることのほうが少ないですから。ただそれに甘えて何年経ってもすぐ聞いてしまうのも考えものです。質問の仕方によっては、あなたの評価を下げてしまうこともあるので注意が必要です。
私は、セミナー講師をしていますが、講義の最後に「何か質問はありませんか」と参加者に問いかけることがあります。すると、たまにこんな質問が来ます。
「営業で売れるコツを一言で教えてください」
はっきり言って、そんなコツがあれば私が教わりたいくらいです。営業はいろんな要素がからみ合って結果が出るもので、そう簡単に答えが出るものではありません。
とくに若手に目立つのですが、すぐに解答を求めたがる傾向があるようです。このような質問をされると、答える側の心理としてはがっかりします。手っ取り早く正解にたどり着きたいという心理が見えて、この人のために誠意を込めて答えたいとは思えなくなります。
ちなみに先ほどの質問に対する私の答えは、
「わかりません。でももし一言で売れるコツを私が知っていたら、その情報を1億円で売るでしょうね」
本当にそんなものが存在するなら、世界中の企業が欲しがります。そこに正解が無いからみんな試行錯誤しているのでしょう。私もまだまだ研究中です。
この手の質問は、言い換えると自分が楽になるための質問です。調べたり考えたりするよりも、さっさと正解を聞いてしまったほうがいいというタイプ。これではいくらやさしい先輩でも、いい気持ちはしないでしょう。
本当に困って聞いてくる部下は可愛い
「すみません、さっきから取説を読んでいるんですが、どうもわからなくて……」
「どうしたの?」
「このコピー機で表裏印刷をしたいのですが、わかりますか?」
この質問はどうでしょう。あなたが先輩だったとしたら、丁寧に教えてあげたくなりますよね。その理由は、知ろうと努力しているのが見えるからです。もちろん、最初から聞いてしまえばすぐに答えがわかるでしょう。そのほうが仕事の効率もいいかもしれません。
しかし、人間関係という意味では、何でもすぐに聞いてくる部下と、自分で調べてから聞いてくる部下とでは好感度が違ってきます。やはり、試行錯誤したうえで頼ってくる部下に愛着がわくのは自然なことでしょう。
これはすべての仕事に共通することですが、人間が行うもので完璧なマニュアルというのはありません。教わった通りにやれば、誰でも結果を出せるということもないのです。
やはり個人でそれなりの工夫をしたり、失敗から学んだり、壁に当たって悩んだりするなど、様々な経験をしながら能力を身に付けて行くもの。それが仕事です。そしてそんなあなたを会社はきちんと評価してくれます。
わからないことがあったら、まずは自分で考えてみること。調べたり試したりしながら正解までの道のりを模索すること。そのうえで、先輩や上司に聞くというクセをぜひつけてください。
「簡単に答えを求めないほうが成長する」ということを忘れないようにしましょう。
これは思い当たる節がたくさんある・・・。
今思えばパワーポイントの使い方やショートカットコマンドなんて検索すれば一発ででてくるのに「あれなんでしたっけ…?」なんて気軽に聞いちゃってたな。(反省)
入社5年目のわたしは後輩も先輩もいる立場、後輩のお手本になるためにもまずは「自分で調べる」ということをクセにしていこう!



「わからない」ことはどんな環境でも発生するよね。
内容も些細なことから難しいことまで千差万別。
シュレッダーの件は結局故障で業者を呼んだんだけどまずは自分で調べたことで「紙詰まり」「ゴミが満杯だった」「紙以外を入れた」「電源コードの確認」などありえそうな可能性は事前に排除できたからスムーズに先輩に報告・相談ができたよ。
今回は「わからないことがあった時」のお話だったけどどうかな?
一度チャレンジしたり調べたりしておくことで聞く時も質問の内容がぐっと具体的になるね。
そういう細かい部分も先輩や同僚はきっと見てくれているよ。
では次の記事でまたお会いしましょう!
お疲れ様です!!