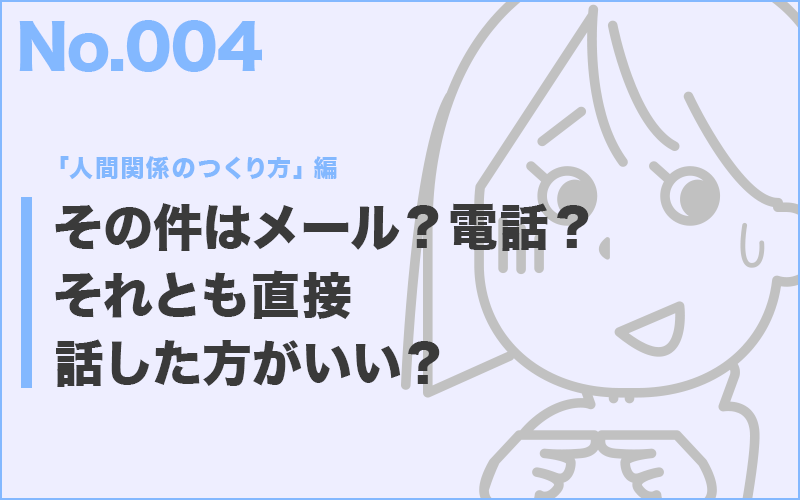今日もネットカフェからこんにちは。
コミュ力ゼロ美です。
ひとり一台スマートフォンが当たり前の時代になってから大分経ちますね。
職場の人とはLINEや社用チャットなどでやりとりしている方も多いと思いますがビジネスの場面では、
まだまだメールや電話が正式なやりとりとしては主流です。
アルバイト先への連絡、上司・同僚へのスケジュール確認、飲み会への参加確認…。
要件によって日々緊急性が違う確認事項が発生する中で皆さんはメールと電話、どのように使い分けていますか?
私は電話がコワいのでついメールにしちゃうときがあるのですが緊急性の高い要件に限って返信がなくて結局電話することになってしまうことがあります。
今回はそんな「メール or 電話」なお話です。
もしよかったら参考にしてくださいね。
その件は、メール?電話?それとも直接話したほうがいい?
渡瀬 謙著 「コミュ力ゼロからの「新社会人」入門」より

メールに頼りがちな人は要注意
ビジネスの場でのコミュニケーションツールとしては、いまや主流は電話よりもメールです。社内のデスクにも固定電話を置かないところが増えていて、個別にスマホを持つのが当たり前になりました。
私も今では仕事のやり取りのほぼすべてはメールで行っています。打ち合わせの日程を決めるときや、書類のやり取りなどもメールです。出不精でしゃべるのが苦手な私にとっては大変ありがたいツールです。
ただ、なんでもメールで済ましていると、たまに電話で話をするときに緊張することもあります。その意味では、メールに慣れている世代には、会社で電話をするということに多少は抵抗感があるかもしれませんね。
とくにトラブルになりがちなのは、電話を使うべきところでメールを使ってしまったケース。
- 緊急の連絡をメールで送ってしまい、トラブルになった
- クレーム対応をメールで行って、相手を怒らせた
- 細かい打ち合わせをすべてメールでやり取りしようとして余計に手間がかかった
メールと電話はそれぞれ特徴があります。それを理解していれば、使い分けるときに迷うことはありません。
急ぎのときは迷わず電話を使うこと
考え方としては、基本はメールを使うこととして、電話を使うべきときはどんな場合なのかを知っておくだけでOKです。
電話の特徴は何といっても相手と直接話ができること。知りたいことがあればその場で聞けますし、確認すべきこともその場でできます。また、普通に会話ができるので、相手の意見や気持ちのニュアンスといった微妙な情報も伝わります。それを踏まえて3つのポイントを押さえておきましょう。
①緊急時の連絡
その日の予定が変更になったり、待ち合わせ場所が変わったなど、すぐに連絡を取らなければならない場合は、電話が第一の選択肢です。つながらなければ留守電にメッセージを残すなど、急ぎの対処をしましょう。
②クレームへの対応
これも緊急時ですが、とくにクレーム対応はスピードが重要です。直接行って対面で対応するのが最も有効ですが、まずは電話で謝罪の気持ちを伝えましょう。そして相手の怒りの声を受け止めます。この受け止める行為はメールではできません。
③至急の意思確認
その場で上司の決裁があれば契約が決まるなど、相手の意思を至急確認したい場合は電話を使います。
また、電話で打ち合わせの日程を決めたときに、確認のためにその後メールで送ることをおすすめします。
日程や金額など、聞き間違えるとトラブルになりやすいものは、メールで「先ほどはお電話ありがとうございました。○月○日の14時に御社にて打ち合わせということでよろしくお願いします」と送っておくと、相手も安心しますし確実です。さらに後々に言った言わないなどのトラブルが起こることも回避できます。
このように、いざというときの対応の仕方が、信頼度を左右します。自信を持った適切な対応を心がけましょう。
基本はメール、特別な場合は電話を使う、ということをベースに要件によってどちらが適切か判断しましょう。
緊急の案件によっては電話とメールの合わせ技も必要だね。
メールか電話かどちらかだけではなく要件によって適切な判断ができるように日頃から意識していこう!
今回は「メールと電話」に関するお話だったけどどうかな?
安易にメールに逃げてきた私は「メール一通・電話一件で大きく人の印象が変わる」ことを覚えておきたいと思います!
では次の記事でまたお会いしましょう!
お疲れ様です!!